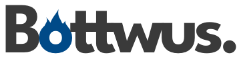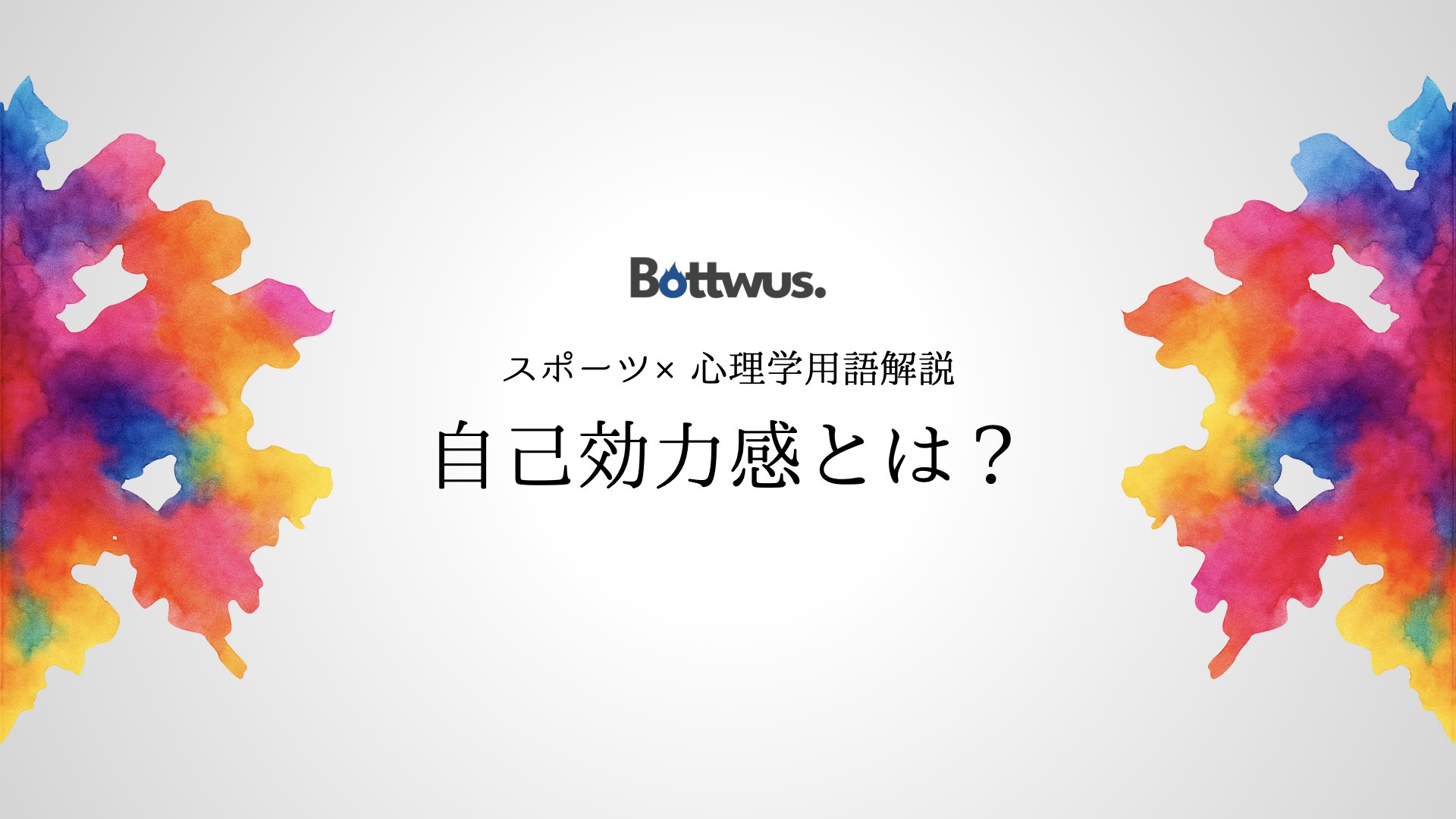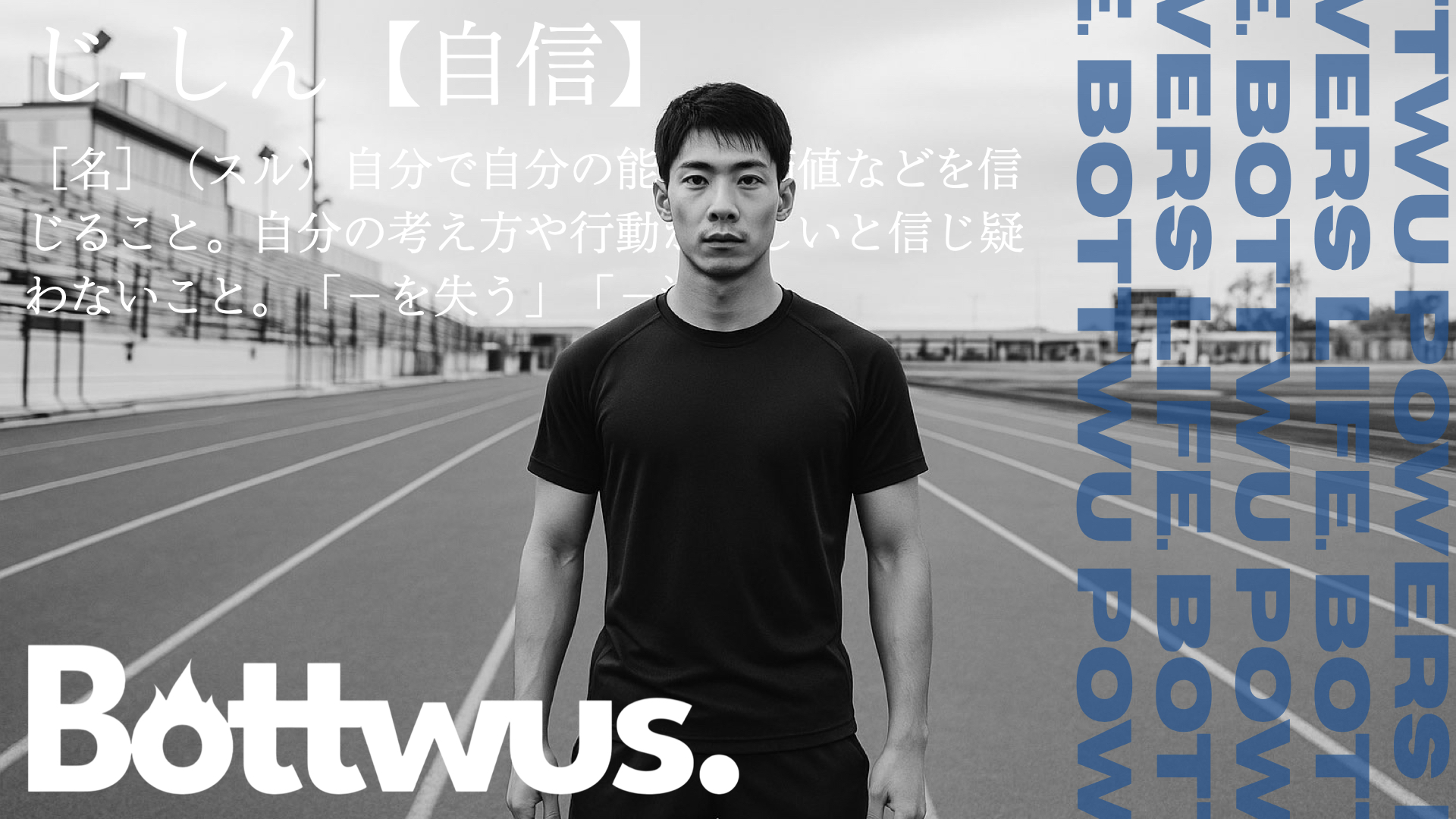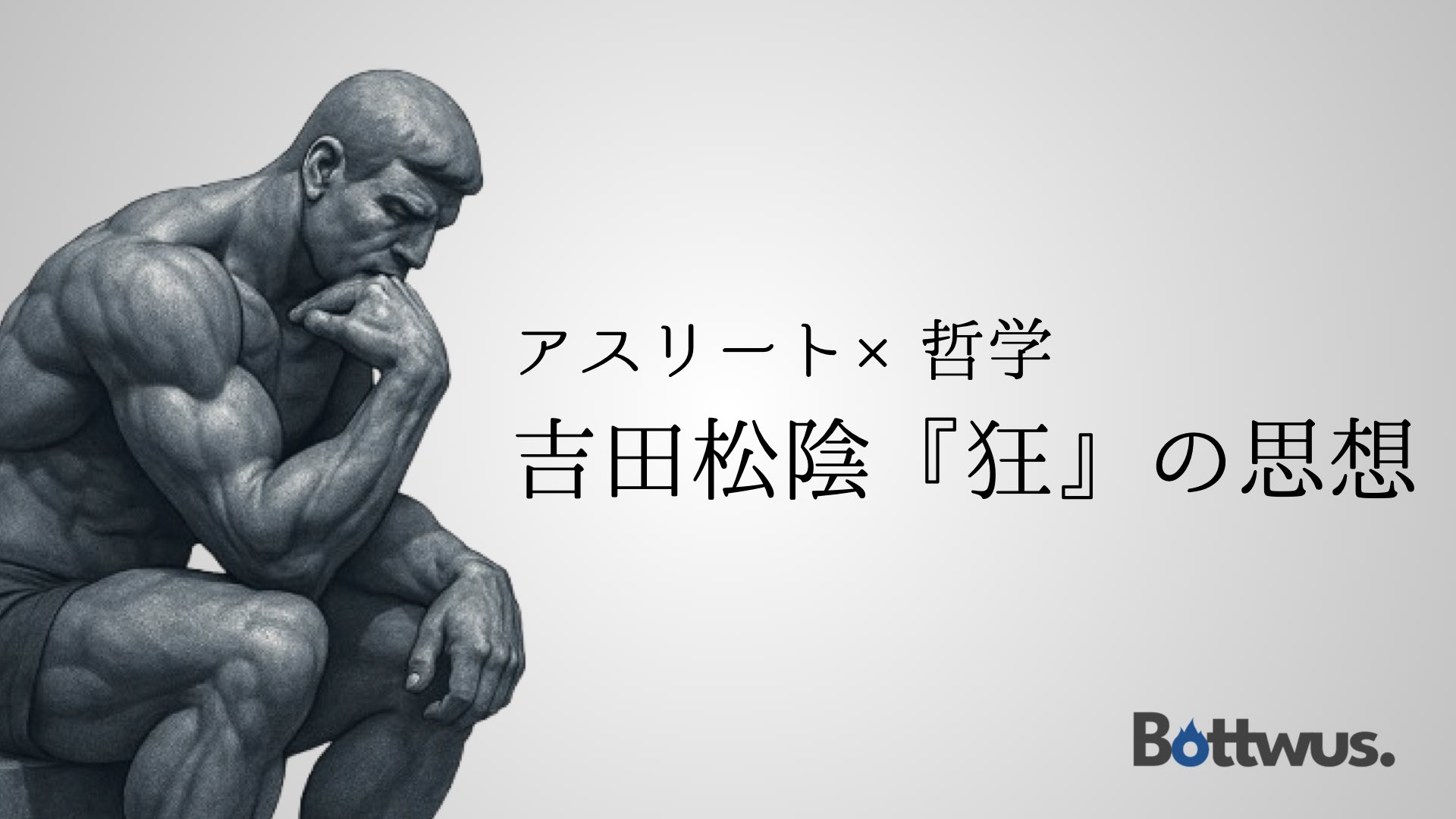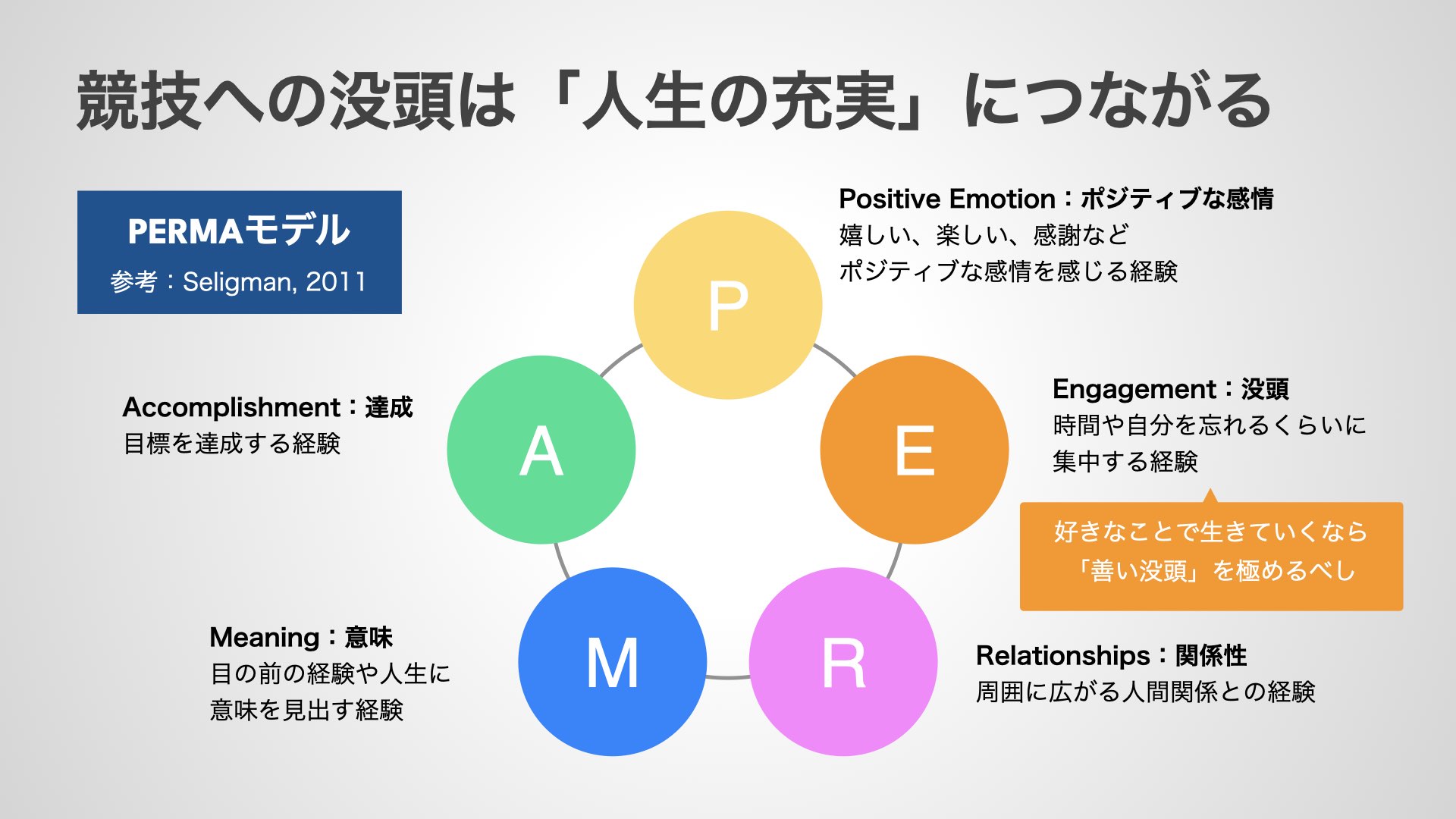「自信がないんです…」
「練習では大丈夫なんですけど、試合になると不安で…」
こういった悩みはアスリートのよくある相談の一つです。
一方で「自分ならできる!」という信念を持った選手ほど、自分のパフォーマンスを発揮し、大会や試合で活躍することができるということもよく目にしてきました。
アスリートが最高の成果を出すためにも不可欠なこの自信について、スポーツ心理学の観点からは自己効力感という概念で説明ができます。
本記事では、自己効力感とは何か、アスリートにとってなぜ大切なのか、そして実際にどう高められるのかをわかりやすく解説します。
自己効力感とは?
自己効力感(Self-Efficacy)とは「自分は特定の状況や課題において、必要な行動をうまく遂行できる」という確信や信念を指します。
単なる自信やポジティブ思考とは異なり、行動の選択・努力の量・困難に直面したときの粘り強さなど、実際のパフォーマンスや成果に直結する心理的要因です。
提唱者
自己効力感(Self-Efficacy)の概念は、1977年心理学者アルバート・バンデューラ(Albert Bandura)によって提唱されました。バンデューラは、人間の行動は先行要因、結果要因、認知的要因という三つの要素が複雑に絡み合い、人、行動、環境の三者間の相互作用の循環によって決定されるとしました。その中でも、特に個人の認知的要因(予期機能)を重要視し、これが行動変容に果たす役割を明らかにしようとしました。

Image: Albert Bandura (2005), Licensed under CC BY-SA 4.0
Photo credit: Albert Bandura via Wikimedia Commons
日常や競技の具体例
自己効力感は日常生活やスポーツの様々な場面で実感することができます。試験勉強をしていて「この問題は解ける」と思えると挑戦しやすくなったり、サッカーのPK戦で「自分は決められる」と思える選手は、迷わず自分のフォームでシュートできたりします。
※自己肯定感との違い
自己肯定感が「自分の存在そのものを肯定する感覚」であるのに対し、自己効力感は「特定の課題や状況で成功できると信じる感覚」を意味します。「自分はOK」とするのが自己肯定感で、「自分は〇〇ができる」が自己効力感です。
自己効力感を形成する4つの方法
①達成経験(Performance Accomplishments)
個人が自ら行動し、必要な目標を達成した直接的な成功体験を積み重ねることで、これからするチャレンジに対しても「できる」という感覚が強化されます。この体験が最も強く安定した自己効力感をつくると言われています。反対に、失敗経験は自己効力感を低下させる傾向があります。
②代理的経験(Vicarious Experience)
他者が成功していることを観察することを「モデリング」と言います。仲間や憧れの選手が成功する姿をみて「自分にもできそうだ」と思えるようになります。特に、自分と似た能力や状況の人物の成功を見ると、その影響は大きくなります。チームの中でお互いの良いプレーを共有することも有効です。
③言葉での説得(Verbal Persuasion)
コーチや仲間からの「あなたならできる」という言葉が自己効力感を支えることがわかっています。これも努力や成果に基づいた、根拠のある声かけであることが重要です。反対に根拠のない言葉だけで高まった自己効力感は直面した時に簡単に失われてしまうと言われています。また自分自身へのセルフトークも効果的です。
④生理学的状態(情動喚起)(Physiological States / Emotional Arousal)
心臓の鼓動が速くなる、手の震えといった身体的反応や、不安、興奮といった情動的状態も自己効力感に影響を与えます。これらの状態をポジティブに解釈できると自己効力感は高まり、ネガティブに解釈すると低下します。
スポーツにおける自己効力感の重要性
スポーツという世界でも、自己効力感は選手のモチベーションとパフォーマンスを理解する上で非常に重要な概念とされています。ここからは実際のスポーツ場面での研究と照らし合わせながら、その重要性についてまとめます。
動機づけと努力の持続
高い自己効力感を持つ選手は、困難な目標を設定し、障害に直面しても努力を惜しまず、粘り強く挑戦し続けます。たとえばGernigon & Delloye (2003) の研究では、自己効力感が高いアスリートは練習や試合において挑戦的な目標を掲げる傾向が強いことが報告されています。
パフォーマンスの向上
自己効力感は、集中力、注意力、ストレス耐性、メンタルヘルスにポジティブな影響を与えます。スポーツ選手対象とした研究では、自己効力感が高いと試合パフォーマンスの安定につながるということが報告されています(Feltz, 2008)
様々な自己効力感の研究をレビューした論文においては、クローズドスキルスポーツのエリートアスリートにとって、自己効力感の向上がパフォーマンスに意味のある影響を与える可能性が高いとされています。(Lochbaum et al., 2023)
困難場面への対処
特にプレッシャーの高い場面やネガティブなフィードバックを受けた際、自己効力感が高い選手は、その影響を緩和し、高い遂行レベルを維持できる傾向があります。
最新のシステマティックレビューでは、自己効力感がスポーツにおけるパフォーマンスやストレス下での遂行力と強く関連していることが改めて示されています。特に、サッカーやバスケットボールなどの集団競技を含む数十件の研究を分析した結果、自己効力感がモチベーション、集中力、ストレス対処に強く関連していることが示されています。(López-Rodríguez et al., 2025)。
これはスポーツ場面ではありませんが、カナダのリハビリ施設において、90名の負傷者を対象に、8週間にわたり「自己効力感」や「リハビリ実施率」を調査したところ“自己効力感とリハビリの継続との間に中程度から強い相関関係”があることを示しました。さらに、自己効力感が高いほど、リハビリの頻度や質、継続が維持される傾向があると報告されています。(Wesch et al., 2012)
まとめ:揺らがない自己効力感を作ろう
自己効力感は「できる」という信念であり、アスリートが挑戦を続け、最高の成果を発揮するための土台となるものです。
スポーツをする中で「できる」と思える根拠を積み重ねる。
これがプレッシャーやストレスのかかる試合や大会でのパフォーマンス発揮につながります。
参考文献
このブログ記事について
記事の引用・参照はご自由にどうぞ。その場合は出典としてリンクを貼っていただけると、より多くのアスリートに情報を届けられます。ご協力よろしくお願いします。